


同志社大学生命医科学部
アンチエイジングリサーチセンター教授
米井嘉一 先生
「老化」についてのふり返り
前回のインタビュー①の先生のお話で老化には2種類あり、病的な老化の対策をすることで老化をゆるやかにできること、また、病的な老化を進める危険因子としてここに挙げた5つを教えていただきました。
<2種類の老化>
- 正常な老化
⇒年相応の緩やかな変化⇒誰にでもおこる、避けられない変化 - 病的な老化
⇒生活習慣などで加速された変化⇒自分自身で対策できる
「個人差」が非常に大きい
<病的な老化の危険因子>
- 分子レベルで老化を促進⇒⇒酸化・糖化・炎症
- 生活の中の危険因子⇒⇒ストレス・生活習慣
食育について
ー先生は、生活の中で意識できる老化対策として、「食育」・「体育」「知育」の3つのバランスを大切にされているとお伺いしました。まずは「食育」について教えてください。
<米井先生>
人間の身体には抗酸化システムが発達していて、身体で作り出すことのできる抗酸化酵素もあります。SODなどの酵素の活性を生かすことが老化対策の一つです。それからフリーラジカル*を消去するような物質を血中に確保することも有効です。ビタミンC、ビタミンE、それ以外の抗酸化物質も果物や野菜に豊富に含まれているので、積極的に摂取し身体の中に保つことが重要です。
食品中のフラボノイドにはAGEs(最終糖化産物)の生成抑制作用があるものが多いです。果物を食べる、野菜を食べることはとても重要なポイントになってきます。そういう栄養成分を凝集したサプリメントも有効です。
*フリーラジカルとは
人の身体を酸化させ、錆びさせる活性酸素の一種

ー飲み物でおすすめはあるでしょうか。

<米井先生>
お茶やハーブティーにもカテキンが入っていますので有効です。カテキンにもさまざまな種類がありますが、AGEs(最終糖化産物)の生成抑制作用があるものが多いです。ジャスミン茶やカモミール茶、さまざまなお茶にAGEsの生成抑制作用があります。
腸内環境と老化の関係は?
ーよく身体の健康は腸からと聞くことも多いですが、腸内環境は老化対策としては影響するでしょうか。
<米井先生>
腸内細菌には善玉菌、悪玉菌がありますが、善玉菌は、酢酸や乳酸を作ります。それもAGEs(最終糖化産物)の生成抑制作用があります。酪酸や酢酸には自分自身の体温を上げる、心拍数を上げる、基礎代謝を上げるという作用があり、太りにくくなるということも期待できます。
ですから、腸内細菌を良い感じに保つということは重要です。
「体育」の大切さについて
ー続いて「体育」について教えてください。
先生の著書で、安静にする生活は避けましょうというのを拝見しました。
<米井先生>
よく病気になると安静第一と言いますが、身体を動かさないという意味の怠け者になってはいけません。老化の仕組みを考えると、人間は使わない組織器官は徐々に機能が衰えます。
頭を使わなければ認知機能が衰えます。筋肉も使わなければどんどん筋力が落ちます。骨も弱くなっていきます。無重力状態で生活したら、骨はもろくなって骨密度も下がります。ですから使うこと、歩けるなら歩くこと、それが生活の質を高めて快適な人生を送ることにつながりますので、体育運動というのは非常に重要です。
ー運動が苦手という方はどうしたらいいでしょうか。
<米井先生>
15分余分に歩くこと、そこから始めるのが良いと思います。また、階段のくだりはおすすめです。人によっては意味がないという方もいますが、階段を登るときは疲れるし、太ももを上げるし、筋トレになるのは確かです。しかし階段を下りる時にも筋肉を使ってるんです。そして着地する時にはちゃんと刺激も骨に伝わるんです。これを、エキセントリック運動と言います。だから最近は階段の下り、山下りが評価されています。
他におすすめは砂浜ウォーキングです。砂浜ウォーキングすると疲れるんです。短期間で疲れる、気分がいい。綺麗な砂浜で景色を見ながらゆったりと15分散歩する。短時間で疲れるから効率的なんです。


ー私たちも日ごろから、頭も身体もしっかり使う生活を心掛けたいと思います。
「知育」の大切さについて
―「知育」の大切さについて教えてください。
<米井先生>
知育っていうのは、まず気力、気の持ち方。病は気から、若さも気から。最近ではキレイも気からと言っています。
気の持ちようは非常に重要なんです。そんな言い方をすると非科学的と思うかもしれませんが、科学的に言えば動機づけ、行動変容なんです。目的意識を持って、気力を持って、それに向かって行動を変えていく。そういう意味で言うと、食育、知育、体育の中で知育が一番重要です。
行動を変えていく。目的意識がないと運動しようという気にもならないですし、それから食事で頑張ろうという気にもならないんですね。だから、そこは衰えて欲しくないんです。
病気は気から。若さも気から。キレイも気から

ーいつまでも元気で健康でいるためには気持ちがやはり大事なんですね。
<米井先生>
気を持つこと、病は気から、老化も気から、キレイも気から、とにかく自分はいつまでたっても若く美しくいるんだ、生きるんだ、そういう気を持ってほしいと思います。まず目標意識を持つ。そしてそれに向かって立ち向かう。1番目にいいことができなかったら、2番目にいいことをやる。
2番目がだめならば3番目にいいことをやる。決してあきらめない。そういう心意気でこれからも向かっていってほしいと思います。
ー毎日の食生活、過ごし方、気の持ちようを工夫し、意識することが大切ですね。
<本日のまとめ>
①生活の中で意識できる老化対策として、
「食育」「体育」「知育」の3つのバランスが大切
②「食育」
1)身体が持つ酸化と戦うシステム、
SOD酵素などの活性を活かす
2)ビタミンC、ビタミンE、フラボノイドやカテキンなど
を意識して、果物や野菜、お茶など摂る
③「体育」
1)使わなければ機能は衰える
2)快適な人生を送るために、
頭を使う、15分でも歩く
④「知育」
1)病は気から。若さも気から。キレイも気から。
2)自分はいつまでも若く、美しくいるという意識と
心意気で行動する。
米井先生に老化対策について教えていただき、3回に分けてお伝えしました。皆さまの若々しい生活を送るための情報としてぜひお役立てください。
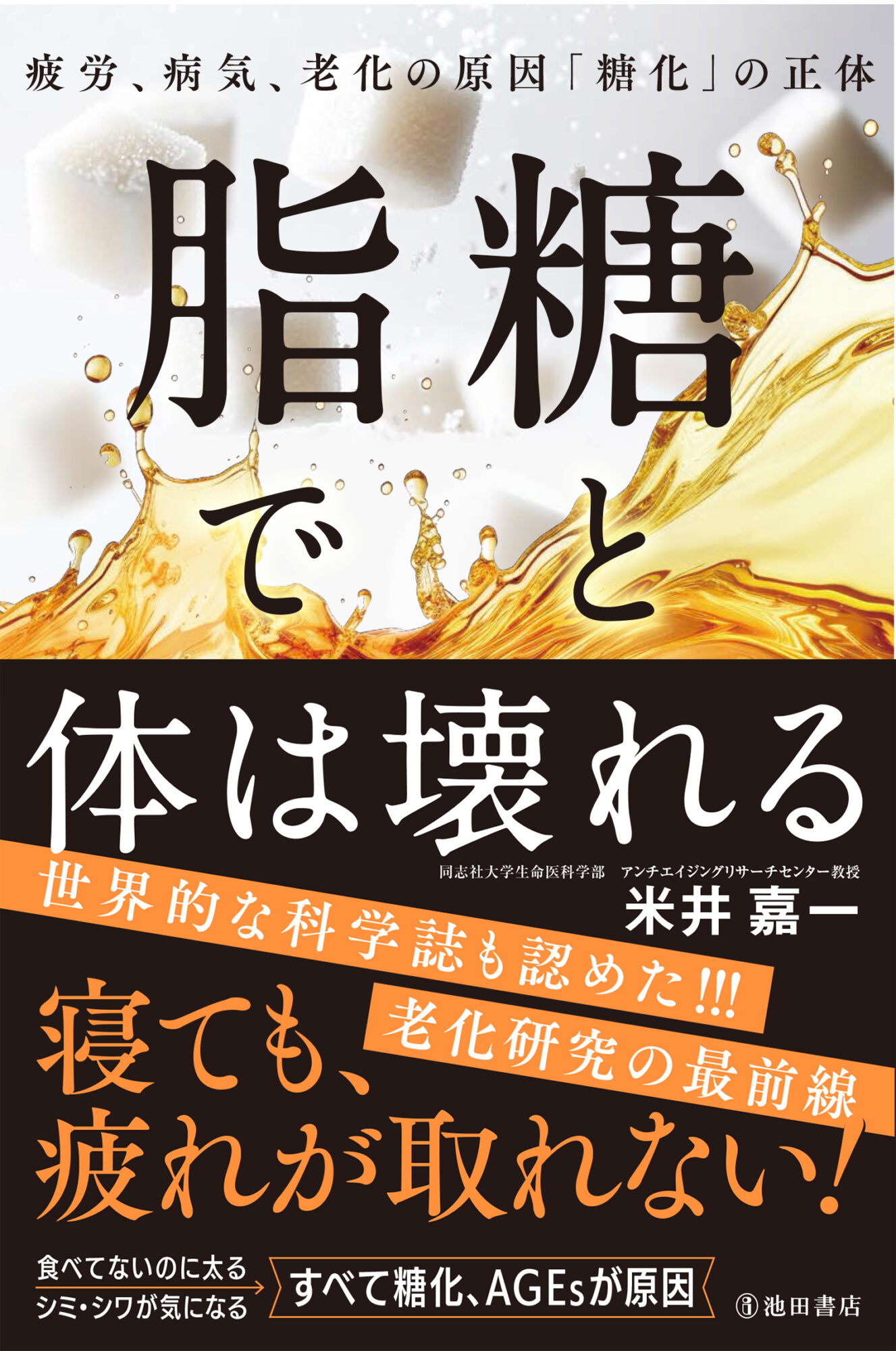
<著書のご紹介>
同志社大学生命医科学部
アンチエイジングリサーチセンター教授
米井嘉一 先生著
(池田書店)
シャルレ編集部

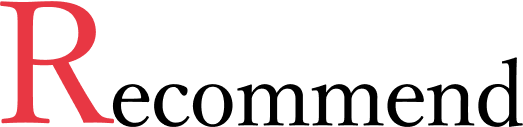
同じカテゴリの記事










リンクをコピーしました


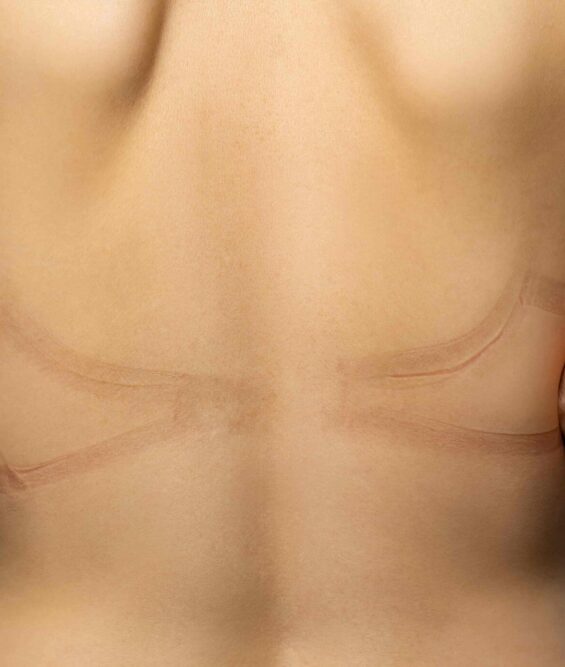
-565x667.jpeg)







